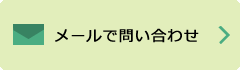マイナンバーカードで医療機関を受診できます(マイナ保険証)
更新日:2025年08月01日
築上町の国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の方へ
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました
従来の保険証が令和6年12月1日をもって廃止となり、マイナ保険証(健康保険の情報が紐づけられたマイナンバーカード)で受診する仕組みに移行しました。
注)このページには、築上町の国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者に向けた情報を掲載しています。社会保険等に加入している方は、ご自身が加入する保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へお問い合わせください。
DV・虐待などの被害を受けている方へ
次のようなときは、DV・虐待などの加害者やその関係者に、マイナンバーカードの情報を閲覧される可能性があります。
- DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者が所持している場合
- マイナポータルで、加害者等を代理人に設定している場合
- 加害者やその関係者が医療従事者等の場合
加害者側からの情報の閲覧を防ぐために
- マイナンバーカードの一時利用停止をすることができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください) - 加害者等が代理人に設定されている場合、マイナポータルから代理人の解除をすることができます。解除方法は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
- 健康保険の情報などの閲覧を制限したい場合は、加入する健康保険の保険者に届出が必要です。
なお、築上町の国民健康保険・後期高齢者医療に加入する方で、住民基本台帳における支援措置(住民票の交付制限など被害者の個人情報を保護する措置)を受けている場合は、自動的に閲覧が制限されます。
令和6年12月2日以降の、医療機関の受診のしかた
マイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書で受診できます。
(「マイナ保険証」の利用登録の方法はこちら。)
「マイナ保険証」を持っている人
マイナ保険証(マイナンバーカード)を医療機関に提示して受診してください。
- 新たに国民健康保険に加入したときや、負担割合が変わったときなどに、資格情報のお知らせを交付します。
- 後期高齢者医療の方には、当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
「マイナ保険証」を持っていない人
保険証に代わる資格確認書を医療機関に提示して受診してください。
- 新たに国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入するときや、保険の内容が(負担割合等)が変わったときなどに、資格確認書を申請によらず交付します。
- 後期高齢者医療の方には、当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
「マイナ保険証」での受診が困難な場合は
マイナンバーカードを紛失したり更新中のとき、病院に行くときに介助が必要な方など、マイナ保険証を使うことが難しい場合は、申請していただくことで資格確認書の交付が受けられます。
- 後期高齢者医療の方には、当面の間、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
「マイナ保険証」の利用登録の解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、保険福祉課保険係に申請してください。
- 築上町の国民健康保険・後期高齢者医療の方のみ受け付けます。その他の健康保険の方は、加入する健康保険の保険者におたずねください。
- 利用登録を解除した方には資格確認書を交付します。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は、入院などで医療費が高額になる場合に、窓口負担を所得に応じた区分の自己負担限度額までにおさえたり、食事代を減額したりするための証書です。
| 後期高齢者医療 | 認定証の発行がなくなり、所得に応じた区分の記載が加わりました。 適用区分の記載を希望する方は、保険福祉課保険係に申請してください。 |
|---|---|
| 国民健康保険 | マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでどおり認定証を交付します。 ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み5.」「一般」の方は、資格確認書等で自己負担限度額が分かりますので、認定証は不要です。 |
- 自己負担限度額は、所得に応じた区分ごとに異なります。
■医療費が高額になるとき(築上町ホームページ)
■入院時の食事代等について(築上町ホームページ) - マイナ保険証には、所得に応じた区分等の情報が連携されているため、認定証の提示は不要です。
- 住民税非課税世帯の方で、過去12か月間に90日を超える入院日数がある場合は、長期入院該当の申請をすることで食事代がさらに減額されますので、入院日数が確認できる領収書等をご持参のうえ保険福祉課保険係に申請してください。
マイナ保険証の有無にかかわらず、申請がないと長期入院該当が適用されませんのでご注意ください。
国民健康保険税に滞納があると
医療費が10割負担になる可能性があります
定期的な分納や特別な事情の届け出がないまま、国民健康保険税を一定期間以上滞納している方については、「特別療養費の支給対象者」に切り替わります(ただし18歳未満の被保険者、公費医療の対象者等を除く)。
「特別療養費の支給対象者」となった場合、医療機関を受診した際に窓口負担が10割になります。
後日、申請することで7割分または8割分が払い戻しとなりますが、その際に払い戻しとなる額を国民健康保険税の滞納分に充てていただくようお願いすることとなります。
引き続き定期的な納付をお願いします
国民健康保険税は、皆さんの医療や介護サービスを支える大切な財源です。
納付期限までの納付が難しいときや、納付が困難な事情があるときなどは、未納のままにせず、お早めにご相談ください。
関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- マイナポータル(デジタル庁)(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(サイト内リンク)