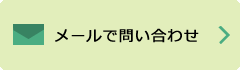国民健康保険税
更新日:2025年5月13日
国民健康保険税とは?
国民健康保険は、私たちの健康を守るための大切な財源で、国・県・町の補助金と国民健康保険税でまかなわれています。
高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満にかかる)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
国民健康保険税が課税される人 / 国民健康保険税の課税 / 国民健康保険税の計算(令和7年度)/
後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置 / 軽減措置 / 特別徴収(年金からの天引き) /
国民健康保険税が課税される人
- 築上町内に住所のある人で、社会保険など他の医療保険に加入してない人は、原則として国民健康保険加入者(以下、被保険者)になります。
- 国民健康保険税(以下、保険税)は、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。(税をおさめる人のことを納税義務者という)
- 世帯主が職場の健康保険(社会保険等)に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば 納税義務者は世帯主となります。(このような世帯主を「擬制世帯主」という)
- 保険税は、被保険者として資格を取得した日(社会保険の離脱や転入の日(注))の属する月から月割りで計算しています。 資格喪失の場合(社会保険の加入や転出)も同様の考え方になります。 (国保の加入、喪失は自己申告になりますので必ず役場 保険福祉課に届け出をお願いします。)
注:国民健康保険の加入や、喪失の届け出をした日ではありませんので、ご注意ください。
国民健康保険税の課税
毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。
年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者のそれぞれの所得に応じて計算される「所得割」、世帯の加入者数に応じて計算される「均等割」、一世帯にいくらと計算される「平等割」を、医療保険分及び後期高齢者支援分(注)と介護保険分(被保険者のうちで40歳から64歳までの人に加算)のそれぞれで下記の税率表により計算し、その合計額を世帯主に課税しています。
もし年度の途中で総所得額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再計算します。
後期高齢者支援分とは
平成20年4月1日から、今までの老人健康医療制度に換わる制度として創設された、後期高齢者医療制度にかかる保険税分になります。
これは制度改正により、後期高齢者医療の4割を、国民健康保険等の各医療保険からの支援によりまかなうことになったためです。
国民健康保険税の計算(令和7年度)
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに均等割額と平等割額があります。これらを全てあわせて国民健康保険税とします。
1. 医療保険分
課税限度額:660,000円
| 区分 | 賦課基準 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額による(注) | 9.0% |
| 均等割 | 被保険者1人につき(人数割り) | 21,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき(世帯割り) | 22,000円 |
2. 後期高齢者支援分
課税限度額:260,000円
| 区分 | 賦課基準 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額による(注) | 3.2% |
| 均等割 | 被保険者1人につき(人数割り) | 6,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき(世帯割り) | 7,000円 |
3. 介護保険分
課税限度額:170,000円(40歳から64歳までの人に加算)
| 区分 | 賦課基準 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額による(注) | 3.3% |
| 均等割 | 被保険者1人につき(人数割り) | 9,500円 |
| 平等割 | 1世帯につき(世帯割り) | 4,500円 |
注意事項
- 基礎総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の所得金額から430,000円を控除した金額です。
- 年度の途中で75歳になる人の後期高齢者支援分は、75歳到達日の(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算しています。
- 年度途中で65歳になる人の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算します。
後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置
後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った人がいたことによって国民健康保険税が急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。
- 所得が低い世帯への軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、世帯の中で被保険者が減っても、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、最高5年間それまでと同様の軽減を適用します。(特定同一世帯) - 世帯に対して賦課される保険税の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる方について平等割を5年間半額にします。 - 被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免
被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行することにより当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になった方(65歳以上)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を課税されていなかったことから、その国民健康保険被保険者の所得割を賦課せず、また、その方が7割、5割の軽減に該当する場合を除いて均等割と平等割を2年間減免とします。
軽減措置
築上町国民健康保険税には、所得が基準以下の額に応じて、世帯への税負担を軽減する目的で、
均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。
なお、世帯の中に所得の分からない人(未申告者)がいると軽減の判定ができないため、軽減できません。
所得の有無に関係なく、国民健康保険の加入者、またはその世帯主は、所得の申告を毎年必ず済ませましょう。
軽減判定の基準
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
|---|---|
| 5割軽減 | 43万円+30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
非自発的失業者の場合
65歳未満で下記に該当する方には、離職翌日から翌年度末までの保険税を算定するとき、前年の給与所得を30/100とみなして行う軽減措置があります。(税務課で申請が必要です。)
- 倒産や解雇などにより離職した雇用保険の特定受給資格者
- 雇い止めなどにより離職した雇用保険の特定理由離職者
後期高齢者医療制度に移行する場合
世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯に国保被保険者がひとりになった場合、その世帯の医療分および後期高齢者支援金分の平等割額が5年目まで2分の1軽減、その後の3年間は4分の1軽減されます。
未就学児の国保被保険者の場合
小学校就学前の国保被保険者は、均等割額が就学前の年の3月末まで5割軽減されます。軽減賦課世帯の場合、5割減額後から7割、5割、2割が軽減されます。
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収の対象となる条件(注)をすべて満たす世帯は、平成20年度から保険税の納付方法が、原則として年金からの天引き(年金特徴)に切り替わりました。
特別徴収の対象となる条件
- 世帯主が、国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が受給している年金額が、年額18万円以上であること
- 保険税の額が、介護保険料の額と合計して特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えないこと
特別徴収の天引き
特別徴収の天引きについて
| 年金受給月 | 補足 | |
|---|---|---|
| 4月 | 仮徴収 | 前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税額を基に、 仮に計算した税額(前年度2月徴収分と同額)を天引きします |
| 6月 | ||
| 8月 | ||
| 10月 | 本徴収 | 確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、 仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします |
| 12月 | ||
| 2月 | ||
普通徴収の納期限
年金からの特別徴収の条件を満たしていない、すべての国民健康保険被保険者の世帯主は普通徴収(納付書及び口座振替にて納付される方)にてお支払いいただきます。
納期・納期限は、下記のページをご覧ください。
保険税の納税には、安全で便利・確実な口座振替をおすすめします
- 口座振替をするには、申込が必要になります。
- 口座振替をご希望の人は、通帳と届出印を持って、町内の金融機関窓口で申込み手続きをお願いします。